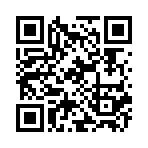2021年07月03日
巨大オブジェ
梅雨の時期なので雨模様なのは仕方がないが、もう7月、夏だと言う気持ちでいっぱい
友人と津でうなぎを食べ、体のだるさを吹き飛ばした
165号線を走って青山方面に行く途中、榊原温泉口の近くに巨大オブジェを見た

ルーブル彫刻美術館の屋外展示物だった


ミロのビーナスとサモトラケのニケ、自由の女神

なんだこれはと驚いたが、1987年(S62年)に開館してたそうだ、すでに34年経過していた
三重県にこんなものがあるなんて、初めて知った


美術館の入り口にはモーゼの像があった




駐車場側にスフィンクスと古代エジプト女性彫像、何も知らずに行くとびっくりする

その後ろに無事カエルという縁起のカエルオーケストラが設置されてあった


そして寶寿山大観音寺方面を見ると


33mの純金観音像が見えた
お寺の入り口側に行ってみると



いろいろなものが置いてあり、外観だけ見て帰宅したが
設計監理:黒川紀章とパンフレットに記載されていた
自宅ではアガパンサス(ムラサキクンシラン)が咲きだしていた



年々花の数が増えてきた、コーヒー粕をまいてた効果が表れたようだ
今年も半分過ぎてしまい、この半年でまた体重が増えてしまった
今年こそ何とかしなければと思いつつ、具体策はない
友人と津でうなぎを食べ、体のだるさを吹き飛ばした
165号線を走って青山方面に行く途中、榊原温泉口の近くに巨大オブジェを見た
ルーブル彫刻美術館の屋外展示物だった
ミロのビーナスとサモトラケのニケ、自由の女神
なんだこれはと驚いたが、1987年(S62年)に開館してたそうだ、すでに34年経過していた
三重県にこんなものがあるなんて、初めて知った
美術館の入り口にはモーゼの像があった
駐車場側にスフィンクスと古代エジプト女性彫像、何も知らずに行くとびっくりする
その後ろに無事カエルという縁起のカエルオーケストラが設置されてあった
そして寶寿山大観音寺方面を見ると
33mの純金観音像が見えた
お寺の入り口側に行ってみると
いろいろなものが置いてあり、外観だけ見て帰宅したが
設計監理:黒川紀章とパンフレットに記載されていた
自宅ではアガパンサス(ムラサキクンシラン)が咲きだしていた
年々花の数が増えてきた、コーヒー粕をまいてた効果が表れたようだ
今年も半分過ぎてしまい、この半年でまた体重が増えてしまった
今年こそ何とかしなければと思いつつ、具体策はない
2021年04月17日
八幡堀
近江八幡の八幡堀では桜の花がすっかり散って新緑を迎えている






かわらミュージアムで漆工芸品の展示会が行われている
友人の漆作家の藤井さんは、2015年に名古屋から近江八幡に移住
現在、滋賀県内でも有名な漆作家として活躍中

漆工芸品の美しい光沢のある艶、その展示会の一部を写真に撮った





日牟禮八幡宮、八幡堀周辺の観光客が、心もち減っているように感じる

路地の至るところに見られた桜が一段落して、所々にピンクの八重桜が咲きだしたようだ

日野307号線沿い「ひばりの公園」でピークに達している
八重桜と牡丹桜の違いが分からないが、満開だ



ふんわりした花がこれでもかと言わんばかりに牡丹のように咲き誇っている

芝桜も咲きだし、だんだん賑やかになってきた
しかし、今日の雨は一日中降っていて、なんだか足が遠のく
かわらミュージアムで漆工芸品の展示会が行われている
友人の漆作家の藤井さんは、2015年に名古屋から近江八幡に移住
現在、滋賀県内でも有名な漆作家として活躍中
漆工芸品の美しい光沢のある艶、その展示会の一部を写真に撮った
日牟禮八幡宮、八幡堀周辺の観光客が、心もち減っているように感じる
路地の至るところに見られた桜が一段落して、所々にピンクの八重桜が咲きだしたようだ
日野307号線沿い「ひばりの公園」でピークに達している
八重桜と牡丹桜の違いが分からないが、満開だ
ふんわりした花がこれでもかと言わんばかりに牡丹のように咲き誇っている
芝桜も咲きだし、だんだん賑やかになってきた
しかし、今日の雨は一日中降っていて、なんだか足が遠のく
2020年10月31日
濃尾平野を一望
今日、友人と濃尾平野が一望できると言われている岐阜県揖斐郡池田町へ行ってきた

中山道赤坂の街道を通っていると、徳川家康も関係していた土地である事を知った



金生山の山頂に向けて、明星輪寺をめざす

山門をくぐっていくと、参道には赤坂虚空蔵ののぼりが見られた


見たことのない植物が咲いていた
後に調べたら秋海棠(シュウカイドウ)という花だった



明星輪寺の本堂に到着すると、濃尾平野が一望できるところがあった


本堂の奥に石灰岩の岩窟があり、本尊の虚空蔵菩薩を参拝する事が出来た


本堂のすぐ近くに、岩に摩崖仏聖観音が彫られていた


牛と虎もいた



参道には様々な菩薩様が置かれている


帰りに307号線の愛東町にあるマーガレットステーションに寄る
家族連れの人達がコスモス畑の中にいて、楽しそうに写真を撮っていた
車から降りて畑の中に入ってみた




天気が良くて、ピンクの花畑の中に入ると、自然と気持ちが和んでくる
中山道赤坂の街道を通っていると、徳川家康も関係していた土地である事を知った
金生山の山頂に向けて、明星輪寺をめざす
山門をくぐっていくと、参道には赤坂虚空蔵ののぼりが見られた
見たことのない植物が咲いていた
後に調べたら秋海棠(シュウカイドウ)という花だった
明星輪寺の本堂に到着すると、濃尾平野が一望できるところがあった
本堂の奥に石灰岩の岩窟があり、本尊の虚空蔵菩薩を参拝する事が出来た
本堂のすぐ近くに、岩に摩崖仏聖観音が彫られていた
牛と虎もいた
参道には様々な菩薩様が置かれている
帰りに307号線の愛東町にあるマーガレットステーションに寄る
家族連れの人達がコスモス畑の中にいて、楽しそうに写真を撮っていた
車から降りて畑の中に入ってみた
天気が良くて、ピンクの花畑の中に入ると、自然と気持ちが和んでくる
2020年09月26日
ふるさと館「旧 山中正吉邸」
日野町に残っている山城跡の詳細資料を展示してあるという事で、ふるさと館へ行ってみた


中に入ってみると、展示室ではパネルで山城を紹介されていたが、撮影禁止となっていた
詳細を記録できなかったが、十数か所の山城が残っていて、蒲生氏、小倉氏の居城だった
後に中野城跡に行ってみたところ
1582年本能寺の変の際に信長の妻子を蒲生賢秀と氏郷が
中野城にかくまって助けた事は歴史上有名な史実で、看板があった


昭和40年(1965年)、日野川ダムの造成で、土塁などが壊され、今は石垣の一部が残っていた

1620年、市橋長政が中野城跡の一部に陣屋を構え仁正寺藩の陣屋として明治維新まで
続いたとの事、現在は草ぼうぼうの広場となっていて、石碑で残されていた
ふるさと館では、デビル磁石式乙号卓上電話機(明治30年(1897年))が展示されていた

台所には大釜付きの五口カマドが残っていた

接客室では手入れされた庭を見せながら対応していたようだ



洋間では当時のチェスが置かれていた

この屋敷の敷地は600坪で、建屋が300坪だそうだ
酒造業を営んでいた日野商人の豪華な生活、接客ぶりがうかがわれた
ふるさと館から外に出ると、反対側に西大路郵便局があり、昭和のポストが現在も使われていた


昭和初期のレトロな雰囲気が残っているところだった
中に入ってみると、展示室ではパネルで山城を紹介されていたが、撮影禁止となっていた
詳細を記録できなかったが、十数か所の山城が残っていて、蒲生氏、小倉氏の居城だった
後に中野城跡に行ってみたところ
1582年本能寺の変の際に信長の妻子を蒲生賢秀と氏郷が
中野城にかくまって助けた事は歴史上有名な史実で、看板があった
昭和40年(1965年)、日野川ダムの造成で、土塁などが壊され、今は石垣の一部が残っていた
1620年、市橋長政が中野城跡の一部に陣屋を構え仁正寺藩の陣屋として明治維新まで
続いたとの事、現在は草ぼうぼうの広場となっていて、石碑で残されていた
ふるさと館では、デビル磁石式乙号卓上電話機(明治30年(1897年))が展示されていた
台所には大釜付きの五口カマドが残っていた
接客室では手入れされた庭を見せながら対応していたようだ
洋間では当時のチェスが置かれていた
この屋敷の敷地は600坪で、建屋が300坪だそうだ
酒造業を営んでいた日野商人の豪華な生活、接客ぶりがうかがわれた
ふるさと館から外に出ると、反対側に西大路郵便局があり、昭和のポストが現在も使われていた
昭和初期のレトロな雰囲気が残っているところだった
2020年07月04日
丸岡城と一乗谷
今日は朝から雨が降ったりやんだり、時々晴れてはまた強く降り出すという天気だったが
友人と福井まで久々に遠出する事になり、まず丸岡城へ行った


以前は天守の屋根が笏谷石(しゃくだにいし・凝灰岩)で出来ていて石の瓦だった

今は銅板の鯱との事
天守から周辺を見ると、雨が降っていて、周辺の山に雲が多かった





徳川の家臣で、本多成重が丸岡藩初代の藩主だった(1613~1646年)
一乗谷へ向かって一乗谷朝倉氏遺跡資料館へ行ったら、残念な事に休館だった
しかし、遺跡がある方へ行き、武家屋敷や庶民の町屋が復原された町並みを見る事は出来た



庶民の暮らしや井戸が各家にあり、武士の部屋の様子が復原されていた








展示された写真の記録から、天皇陛下も来られていた様子が伺えた

桔梗が植えられていて、明智光秀が近辺にいた事を示していた


450年前に、この城下町に多くの人が住んでいたという
朝倉義景が住んだ館の跡が残され、土塁と濠で囲まれていた




雨が降ったりしていたが、ちらほらと観光客が途切れることなく出入りがあった
入場料を払って入館する施設は、何処も検温とマスク着用だった
友人と福井まで久々に遠出する事になり、まず丸岡城へ行った
以前は天守の屋根が笏谷石(しゃくだにいし・凝灰岩)で出来ていて石の瓦だった
今は銅板の鯱との事
天守から周辺を見ると、雨が降っていて、周辺の山に雲が多かった
徳川の家臣で、本多成重が丸岡藩初代の藩主だった(1613~1646年)
一乗谷へ向かって一乗谷朝倉氏遺跡資料館へ行ったら、残念な事に休館だった
しかし、遺跡がある方へ行き、武家屋敷や庶民の町屋が復原された町並みを見る事は出来た
庶民の暮らしや井戸が各家にあり、武士の部屋の様子が復原されていた
展示された写真の記録から、天皇陛下も来られていた様子が伺えた
桔梗が植えられていて、明智光秀が近辺にいた事を示していた
450年前に、この城下町に多くの人が住んでいたという
朝倉義景が住んだ館の跡が残され、土塁と濠で囲まれていた
雨が降ったりしていたが、ちらほらと観光客が途切れることなく出入りがあった
入場料を払って入館する施設は、何処も検温とマスク着用だった